更新日:2019年3月18日
糸数壕(アブチラガマ)
玉城村糸数にある全長約270mの病院壕。当初陸軍壕や住民の避難壕として使用していたが、戦況が激しくなるなか4月下旬より病院壕として使用される。1000名近くの傷病兵を収容していたという。5月下旬撤退命令によりひめゆり部隊等は砲弾のなか南部へ向かう。
自力では歩行できない傷病兵は毒薬を盛られ、叉は置き去りにされた。その後、壕に残った敗残兵や住民等の壕内での避難生活は8月下旬まで続いた。傷病兵の治療も薬品等の不足にてままならず、麻酔せずに手足を切り落とすこともあったとのこと。戦況の趨勢が決したのちも、投降の呼びかけには応ぜず(応じれば敗残兵に殺害される)、米軍は火炎放射等にての攻撃を行った。現在も火炎放射の黒焦げの跡、及び爆風の跡等あり。

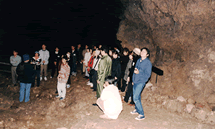

壕の使用経過
| 1994年 | |
|---|---|
| 夏 | 第9師団だい19連隊第1大隊(武部隊)が整備を始める。 沖縄守備軍は米軍の上陸地点を港川海岸と予想し部隊を配置。 |
| 12月5日 | 第32軍主力の武部隊、台湾へ移動 |
| 1945年 | |
| 2月1日 | 三田連隊が配置される。 |
| 4月 | 米軍が中部に上陸したため三田連隊は中部戦線に移動、壕は再び住民が使用。 |
| 4月24日 | 南風原陸軍病院の糸数分院として指定。ひめゆり学徒の一部も移動。 |
| 5月25日頃 | 糸数分院南部撤退命令。病院は解散。歩けない重傷兵は「処置」される。 その後軍民雑居となる。 |
| 6月1日頃 | 米軍地上を占領 |
| 6月23日 | 司令官牛島中将、摩文仁で自決 |
| 8月22日 | 避難民、敗残兵投降 |
| 9月 | 最後の住民と兵隊が投降 |
糸数壕での証言
 |  |
|---|---|
| 壕内の井戸 | 空気穴の跡 |
| 糸数壕は最初に空気穴が米軍に見つかり黄燐弾(燐の空気に触れると自然発火する性質を利用した爆弾)を投げ込まれた。 沖縄戦当時、避難民、軍人にとって水の確保は重要であった。糸数壕は壕内に井戸があるため恵まれていた。危険をおかし水くみに出る必要がなかった。 | 空気穴の跡、糸数壕では最初に空気穴が見つかり攻撃を受けた。地上は米軍の支配下にあり、このような地上から地下の壕への攻撃を馬乗り攻撃と呼ばれおそれられた。 |
日比野 勝廣さんの手記(「歩く・みる・考える沖縄」より)
仰向けに寝ていると背の下にムズムズしたものを感じ、それらがやがて首筋、お尻の下にも感じられる。手探りでつまんだら、それは大きな「うじ」で群れをなしていた。
どこから来たものか、あたりを見まわした時、ふと隣の吉田君(東京)がいつの間にか死んでいた。そしてすでに腐り始め、そこからはい出していることがわかる。
死臭鼻をつき吐き気さえ感じていたが、まさか一番元気だったこの人が、死んでいるとは意外だった。そういえば自分を殴らなくなっていた。水のとりこになっている間に「うじ」の住居になるなど、悲しくも哀れである。
悪臭と「うじ」に悩まされつつも白骨化していく友の傍らから離れるだけの体力もなく、「今にこの姿になるのか」と恐ろしい戦慄の時が続いた。それでも水を求める私は手近なところに水のあることを思いついた。「小便を飲もう」私は一心に放尿に励んだ。しかしこの妙業も効き目がなかった。小便になるような水分は体の中に残っていない。
ある日、向こう側の上部にある空気穴から黄燐弾が投下され、大音響と共にはねとばされた。気を失ってしまった。気ずくと棚の上から落ちていた。他の者も幾人か吹き飛んだらしい。しばらくして正気に戻り「ああ、まだ生きていたか」と辺りを見ると、ここは五米ばかり下の水たまりの傍であった。爆風で飛ばされた時、奇跡的に地下水の流れへ運よくいったものとみえる。
一念が通じたのか、偶然なのか、私の切望した水が得られたことに喜びを感じる暇も惜しく、一気に飲み続けた。痛みも忘れとにかく腹一杯になるまで飲み続けたことは今でも覚えている。水腹であっても満腹感は私に「生命力」を与えてくれたのか、眠りを誘い、起きてはまた飲みして少しずつ動くことが出来るようになった。


